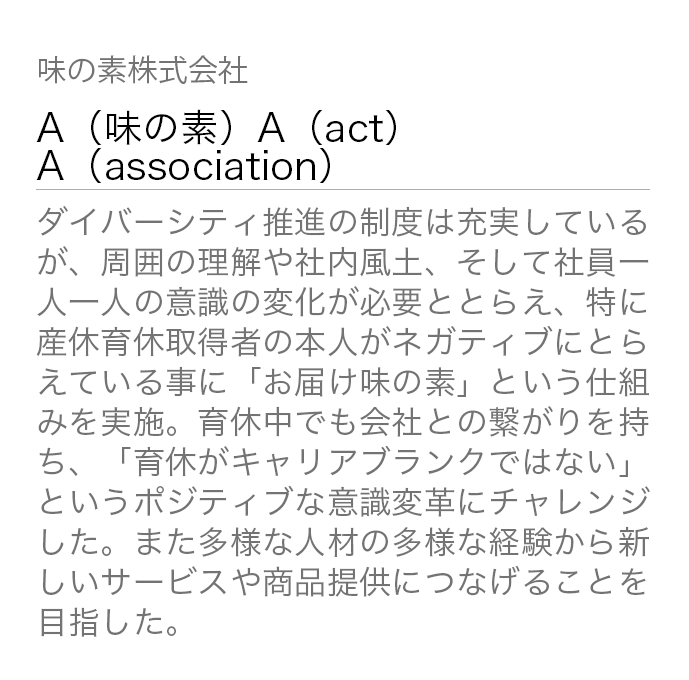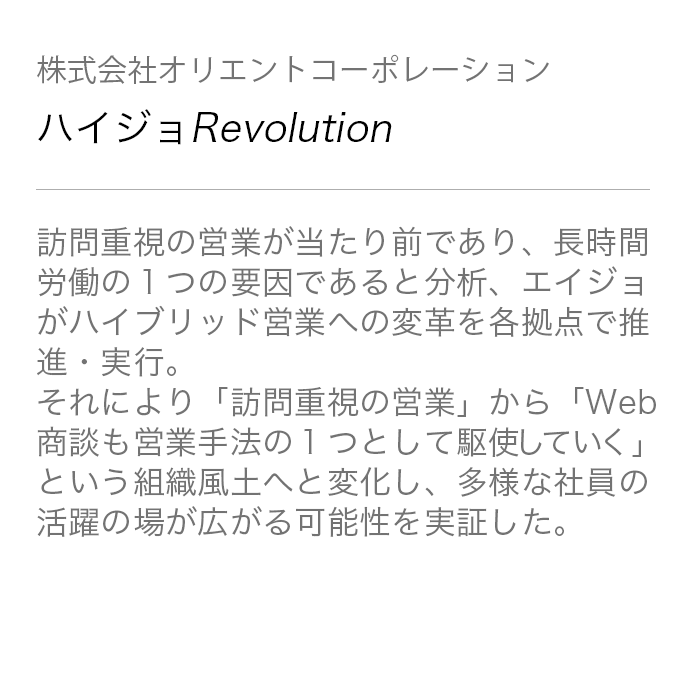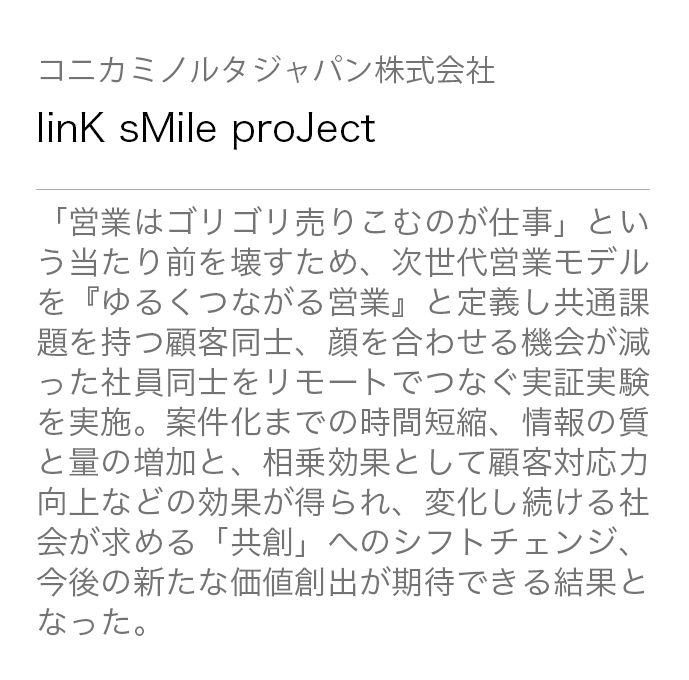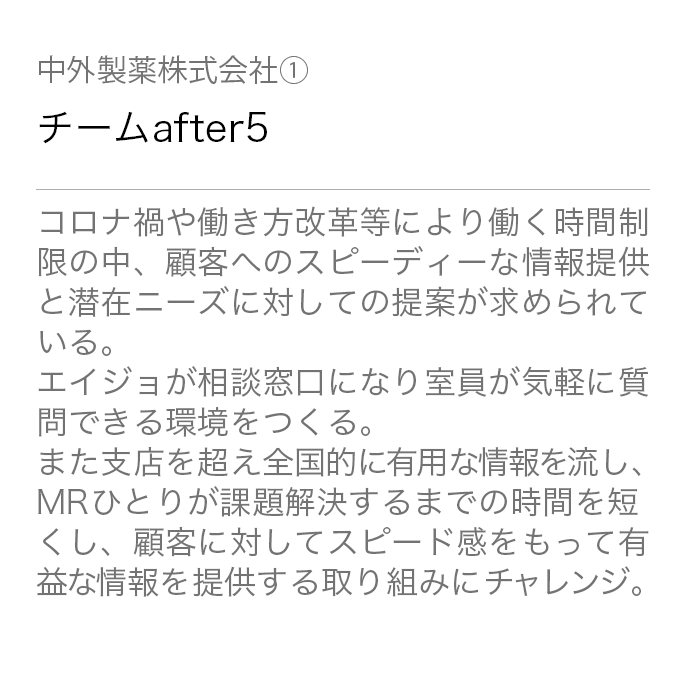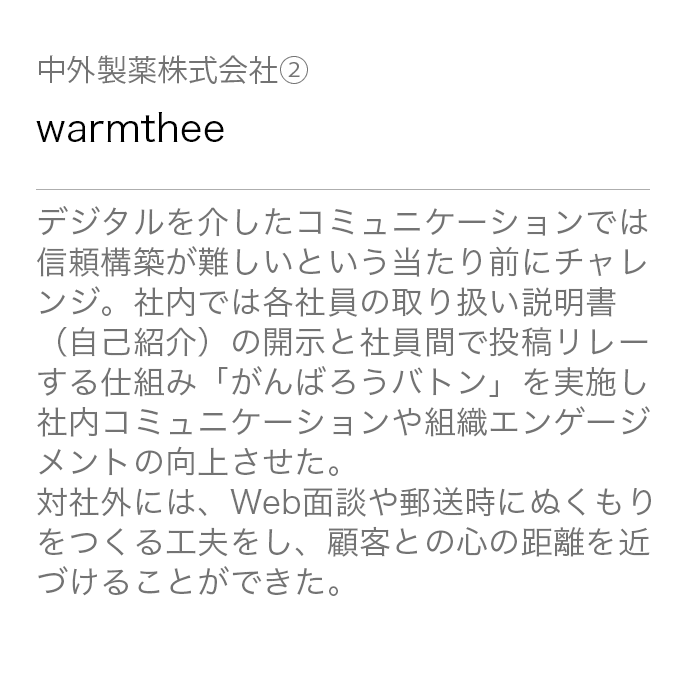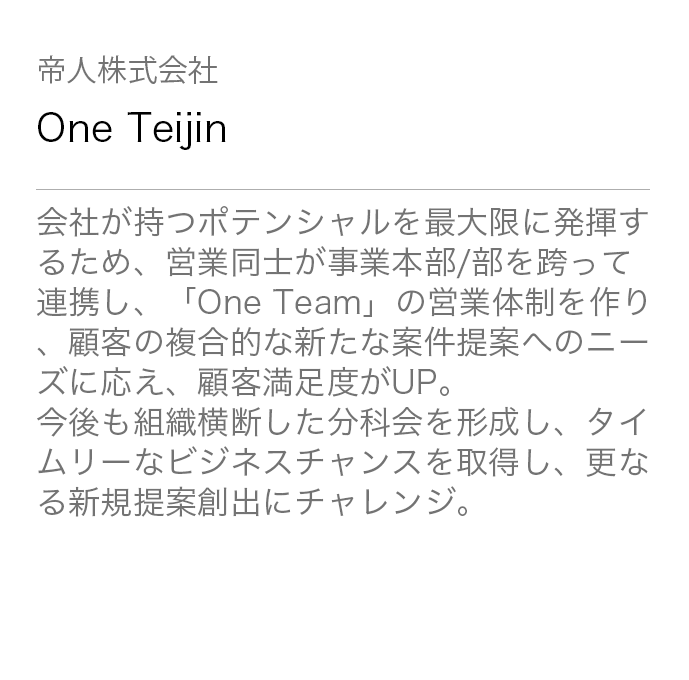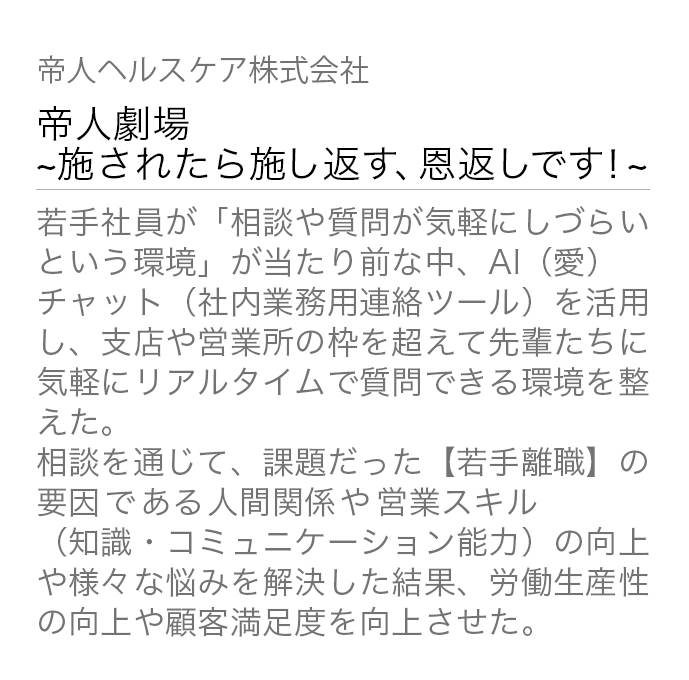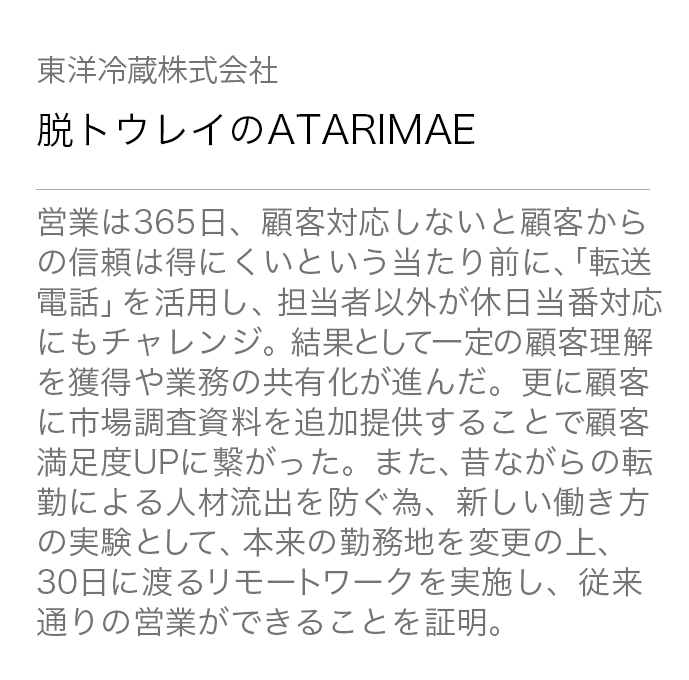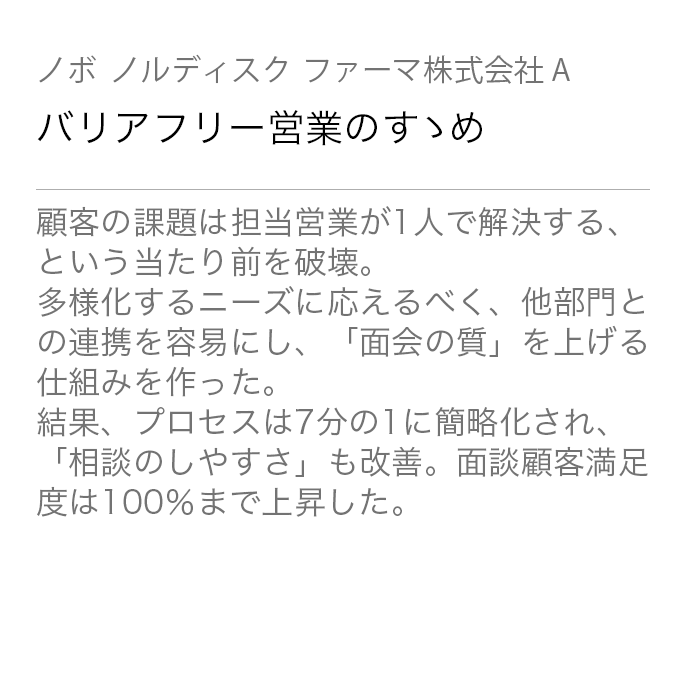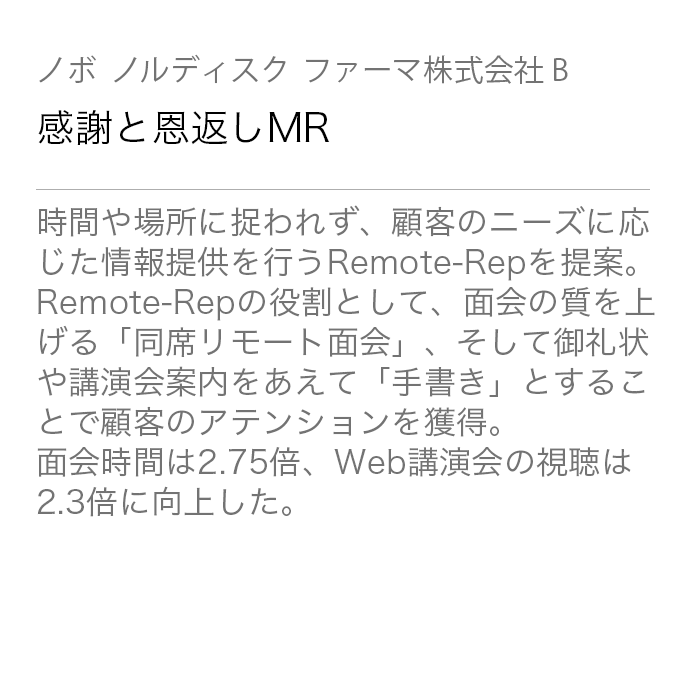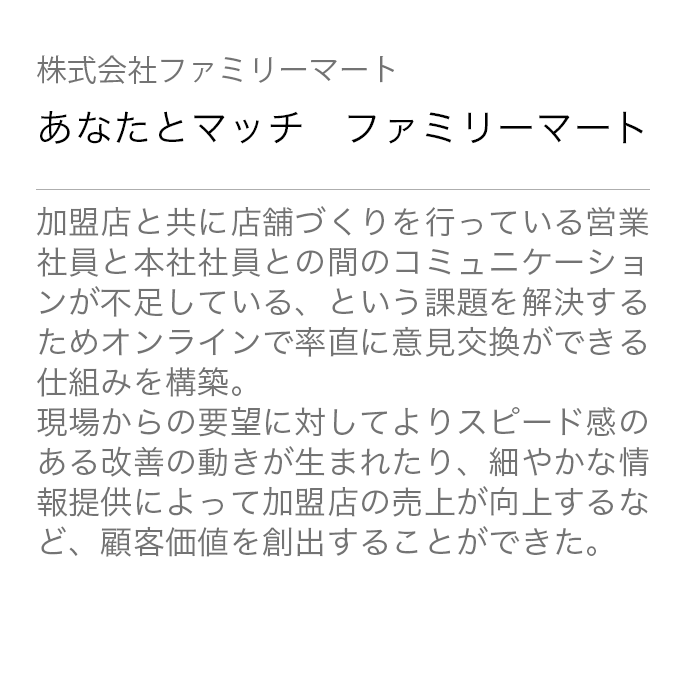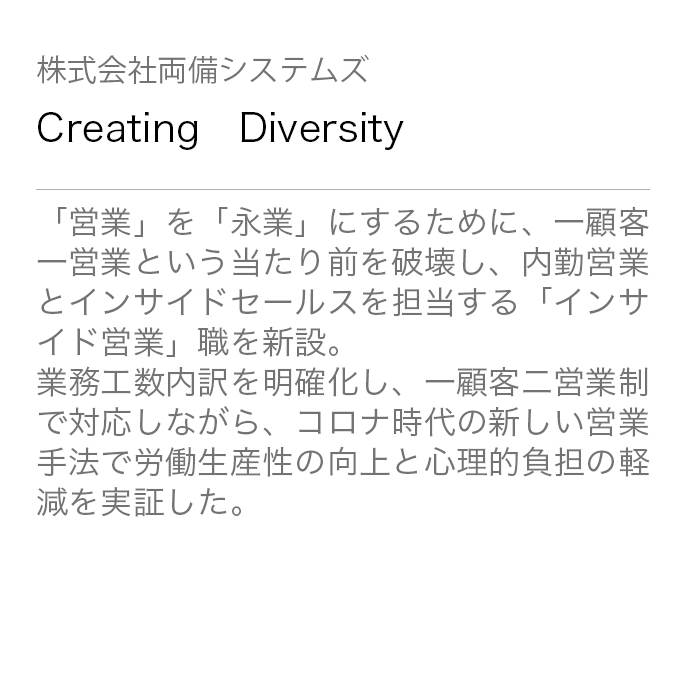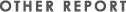EIJYO COLLEGE SUMMIT 2020
2021年2月17日、「新世代エイジョカレッジ(エイカレ) サミット2020」を開催いたしました。
今期のテーマは
Withコロナ時代の次世代営業モデル 〜New Normalは次世代が創る〜
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、パラダイムシフトが起きた2020年度。その変化を追い風として、20社107名の営業女性(エイジョ)が自分・会社・社会の当たり前を問い直し、新しい価値を創出する、変革の実証実験に挑みました。
エイカレ史上初のオンライン開催となったサミットは、ファイナリスト6社の最終プレゼンテーションと、ゲストセッションとして慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授の前野隆司氏にご講演をいただきました。
エイカレ2020 ファイナリスト プレゼンテーション
参加18チームの中から、事前選考を勝ち抜いたファイナリスト6チームが、オンラインにてファイナルプレゼンテーションを披露しました。
【テーマ】
Withコロナ時代の次世代営業モデルの創出
自分たちの会社、また業界の「当たり前」を疑い労働生産性を上げる
クライアントの変化に対応する顧客価値の追求
【審査基準】
- 破壊と創造:営業の当たり前について、課題を適切に把握し、破壊と創造にチャレンジしている
- 労働生産性:実験開始前後/前年同月比で定量的に比較し、労働生産性が落ちていない
- 顧客価値: より高い顧客価値の提供が出来たか・その可能性があるか
- 巻き込み力:個人だけではなく上司や組織等のサポートが得られている
- 汎用性がある:組織、業界を超えて全体に広がりうる
【審査員】
川村美穂氏 経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室長
佐藤博樹氏 中央大学大学院 戦略経営研究科教授
白河桃子氏 昭和女子大学客員教授 相模女子大学大学院特任教授
太田彩子氏 一般社団法人 営業部女子課の会 代表理事 兼 Founder
エイカレ参加企業 役員等 10名
実行委員会 代表 株式会社チェンジウェーブ
オーディエンス票(1票)
エイカレ2020 大賞
「#マネチャレ!」 三井住友海上火災保険株式会社
私達のライン課長チャレンジ!マネチャレ!

#マネチャレ!チームが考えた次世代営業のイメージは、イノベーションを起こし続けるフレキシブルな営業。
そのためにマネージャー層に多様性は不可欠と考えたものの、現状では企業営業部門の女性課長は1人。アンケート調査などから、営業女性たち自身に潜む「マネジメント職は無理」というアンコンシャスバイアスを払拭することが必要ではないかと設定しました。
実証実験では、他課のマネージャー(ライン課長)の業務を体験してみるというマネージャーチャレンジ・略して「マネチャレ」に、23人の営業女性が挑戦。
「私には無理」が「私でもできそう」に変化し、前向きに管理職を目指すマインド変化が起こったそうです。
「今まで見ていなかった『大局感』という視点を得ることができ、意識変革につながった」という声も。
これまでも新任課長研修などは実施されているそうですが、「百聞は一見にしかず」、実体験からの学びは何よりも効果があったようです。
会場からも、
- 「想像してみろ、と言われても上司の立場になるまでは何も分からなかった。経験することは何にも勝る学び」
- 「お互いの仕事を理解することで上司部下の関係性が良くなり、フォロワーシップの強化にもつながりそう」
とのコメントが寄せられました。
大賞が発表された際、#マネチャレ!チームの皆さんが「このメンバーでやり抜けて良かった」と号泣していたのが印象的でした。
彼女たちはマネチャレ制度化に向けて人事部への提案を始めたそうです。「自分たち自身が作っていた『ガラスの天井』を突破して、会社の持続的成長と顧客価値の実現につなげていきたい」と今後の展望を話してくれました。


エイカレ2020 審査員特別賞
「KKCheer's」 協和キリン株式会社

コロナ禍では、対面での人脈構築が難しくなり、現場でのスキル向上も困難になるなど、人材育成においても様々な問題が浮上しました。社内の人間関係が希薄になったと感じる人も少なくないはず。
彼女たちの顧客である医師のニーズも、「面会頻度より、質を重視したい」と変化してきたそうです。
そこで KKCheer’sは、 アフターコロナでも活用が可能な「WEBを活用した人材育成システムの創出」に挑み、 社員が作るナレッジ動画で労働生産性と顧客価値がどの程度上がるかを実証実験しました。
実験では、社員が自ら企画・出演する動画を作成。「顧客視点の話し方」、「効率的な面会方法」、「ニーズキャッチ」等の その日から使えるようなテクニック動画や、普段は聞けない「上司の熱い話」や、「ママ MRの業務効率化ナレッジ」、「ベテラン MR働き方」など、 人にフォーカスしたマインドアップの動画など、全 17本を配信しました。
実証実験期間中、最も関心の高かった動画の視聴回数は 500回。何度も見返して、理解度を向上させる社員が多くいたという結果に。
実際に、動画視聴後のノウハウ実践等によって、訪問件数は 2.3倍に増加。労働生産性は大きく向上し、 99%の人が今後も継続してほしいと希望しました。
このほか、若手社員に向けては、オンライン OJTの仕組みも新たに確立しました。
KKCheer’sの取り組んだシステムは、 どんな人でも主体的に学ぶことができ、勤務地や年代・役職によって、情報格差が生まれることもありません。
与えられる教育から、与え合う教育へ。まさに、リアル対面を超える「質の高い学びのプラットフォーム」を創出しました。
他4チームのファイナリストの最終プレゼンも素晴らしく、オンライン会場はたくさんの拍手(エフェクトとアイコン)で溢れました。
異業種の「学び合い」、事前審査会で他社チームと切磋琢磨してきた成果が見られたように思います。
特別ご講演・前野隆司氏「幸福学入門」

エイカレサミットでは、毎年有識者による特別講演を行っています。今回は、 Well-being研究の第一人者である慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授の前野隆司氏に、「幸福経営学」の特別入門編をご講演いただきました。
世界経済フォーラム( WEF)に向けても、コロナ禍の今年は「グレート・リセット」というテーマが話題になりました。経済成長を目指す社会から、人々の幸せを考えていく社会へと、大きなリセットをしていくべきだという方向性が示されたのです。
社員が幸せに働ける環境を整えることが、なぜ必要なのか。「幸せと生産性・創造性」の関係などを、ご講演いただきました。
Well-beingとは何か
前野氏は、幸福を「あるタイミングの嬉しい!ラッキー!ハッピー!といった限定的な期間の感情よりも、もう少し長いタイムスパンで感じる幸せ、良好な状態」と定義し、それが「well-being」であると説明されました。
幸せな人は、そうでない人に比べて、こんなメリットがあるそうです。
・創造性が3倍
・生産性が1.3倍
・売上は37%UP
・欠勤率が低い
・離職率が低い
・健康長寿になる
幸せに生きていくことが、社会でより良く生きていくことにつながる。また、社員の幸せに気をつけて経営することで、企業の業績を健全に上げていくことができるのです。
Well-beingが先進国で最下位の日本。幸福度を高めていく鍵は?
健康や安全性では世界トップクラスである日本ですが、「国内の時系列で見ると、自己肯定感が下がってきているように感じる」と、前野氏は幸福度の現状に懸念を示されて
います。
幸福学の基礎として紹介されたのは、2つの法則。
❶ 地位財型(金・モノ・社会的地位)の幸せは長続きしない
❷ 非地位財型(環境的安全・健康・心の状態)の幸せは長続きする
また、この心の状態について、前野氏の研究では、その因子も明らかにされています。
幸せな心の状態を作る4つの因子
1. 自己表現と成長(やる気に溢れている人は幸せ)
2. つながりと感謝(ありがとうの気持ち)
3. 前向きと楽観(なんとかなる)
4. 独立と自分らしさ(ありのままに)
自己実現や独立に関連するものとして「主体性」がありますが、主体性と幸せは密接に関係します。仕事内容ではなく、その仕事に主体性を持って取り組めているかどうかが重要となるそうです。
前野氏は、「日本国内でのwell-being経営のトップ企業は、もはや営業目標を作ることをやめている。トップが作った目標にはやらされ感しかないので、現場の社員が自ら目標を作り、自分たちでその目標を管理していくスタイルに進化している」と紹介しました。
また、イノベーションにチャレンジしていく際に、失敗はつきもの。「失敗はダメだ」という空気はNGで、チャレンジを称え合う環境の方が、創造性も高まり、イノベーションも生まれやすくなるそうです。
「日本人は遺伝的に、石橋を叩いて最終的に渡らないタイプ。ただ、遺伝の影響は半分。、意識することでなんとかなる。
心配性遺伝子を乗り越えていくためのポイントは、みんなでチャレンジすること。日本人は農耕民族なので、集団でチャレンジすることが有効だと思う」と前野氏から参加者にエールが送られました。
コロナ禍の今年度は、エイカレ全体がオンラインの開催となり、大きなチャレンジの年となりましたが、素晴らしい実証実験の数々から、また新しい波を作り出すことができました。
エイジョの頑張りはもちろんのこと、審査員の皆様、参加企業の事務局の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。
これからも、新世代エイジョカレッジは、皆さんと共に変革を起こして参りたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
EXPERIMENT SUMMARY
ファイナリスト